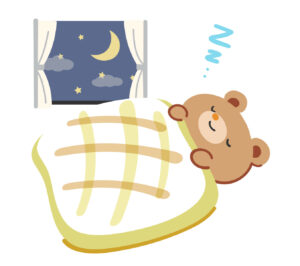こんにちは、にしあかし歯科です。
「また口内炎できちゃった…」
そんな憂鬱な経験、多くの方がお持ちではないでしょうか?
口内炎が気になってご来院される方も少なくありません。
そこで今回は、厄介な「口内炎」について、その種類・原因・対処法をわかりやすく解説します!
正しい知識を身につけて、つらい口内炎と上手に付き合っていきましょう。
先ず、口内炎ってどんな種類があるの?原因は?について解説します。
一口に口内炎と言っても、実はいくつかの種類があります。代表的なものをご説明します。
1.アフタ性口内炎(潰瘍性口内炎)
もっとも一般的に見られる口内炎です。
原因: はっきりとは解明されていませんが、ストレス、疲労による免疫力低下、睡眠不足、栄養不足(特にビタミンB群の欠乏)などが関与すると考えられています。
症状: 頬の内側、唇の裏、舌、歯ぐきなどに、赤く縁取られた2~10mm程度の白い円形の潰瘍(かいよう)ができます。小さなものが2~3個群がってできることも。
特徴: 通常、10日~2週間ほどで自然に治り、跡は残りにくいです。
2.カタル性口内炎
物理的な刺激によって起こる口内炎です。
原因: 入れ歯や矯正器具の不適合による接触、誤って頬の内側を噛んでしまった傷からの細菌繁殖、熱い飲食物や薬品による刺激などが挙げられます。
症状: 口の粘膜が赤く腫れたり、水疱(すいほう)ができたりします。アフタ性とは異なり、潰瘍の境界が不明瞭なのが特徴です。唾液の量が増えて口臭が気になったり、口の中が熱く感じたり、味覚がわかりにくくなったりすることも。
3.ウイルス性口内炎・カンジダ性口内炎
ウイルスや真菌(カビ)の感染が原因となるタイプです。
ヘルペス性口内炎(口唇ヘルペス): 単純ヘルペスウイルスが原因。主に唾液などを介した接触感染や飛沫感染でうつります。小さな水疱が多発し、それが破れてびらん(ただれ)を生じ、発熱や強い痛みを伴うことがあります。
その他のウイルス性口内炎: 梅毒・淋病・クラミジアといった性感染症(STD)が原因で口内炎ができることも知られています。
カンジダ性口内炎: もともと口の中に存在する常在菌の一種であるカンジダ菌(真菌)が、免疫力の低下などをきっかけに異常増殖して発症します。口の中に白い苔のようなものが付着するのが特徴です。
4.アレルギー性口内炎
特定の食べ物、薬物、歯科治療で使われる金属などが刺激となり、アレルギー反応として口内炎が起こります。
5.ニコチン性口内炎
喫煙習慣により、口の中が長期間熱にさらされることで発生します。
特徴: 口の粘膜や舌に白い斑点(白板症:はくばんしょう)ができ、これが癌に変化するおそれもあるため、特に注意が必要です。
口内炎ができてしまったら?心がけたい7つのこと
種類によって原因は異なりますが、できてしまった場合に共通して心がけたいポイントをご紹介します。
十分な休息と規則正しい生活:
ストレスや疲れを溜めず、免疫力を高めることが基本です。
栄養バランスの取れた食事:
特に粘膜の健康を守るビタミンB2、B6などのビタミンB群を積極的に摂取しましょう。
口腔ケアの徹底:
うがい薬や洗口液で口内を清潔に保ち、乾燥を防ぎましょう。
刺激物の回避と食事内容の見直し:
辛いもの、熱すぎるもの、硬いものは症状を悪化させる可能性があるので避けましょう。また、糖質の多い食事はビタミンB群を過剰に消費するため、摂りすぎに注意が必要です。
器具のチェックと調整:
入れ歯や矯正器具が当たって痛い場合は、歯科医に相談して調整してもらいましょう。
身の回りの清潔:
(特にウイルス性が疑われる場合)普段使っているタオルや食器を清潔に保つことも大切です。
早めの医療機関受診:
なかなか治らない、症状がひどい、頻繁に繰り返すといった場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。
お口の中は、呼吸、会話、食事と常に外部と接しており、細菌やウイルスが付着・侵入する可能性が高いデリケートな部分です。
そのため、免疫力を高めておくことと、口腔内の環境を清潔に整えておくこと、この両方が非常に大切になってきます。
少しでも異常を感じたり、不安なことがあれば、遠慮なく検査や相談にいらしてくださいね!
明石市、西明石駅徒歩1分の歯科医院
にしあかし歯科 Tel:078-925-3333