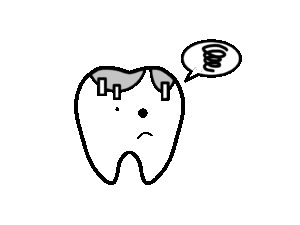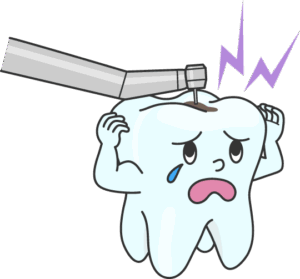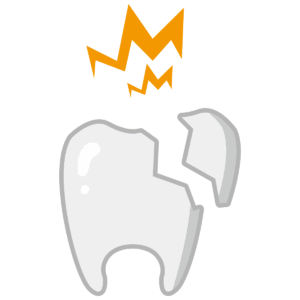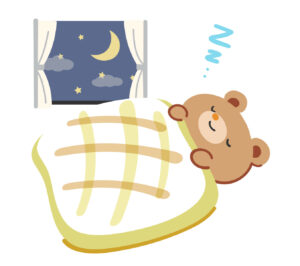こんにちは!
今回は、毎日のオーラルケアを手軽にアップグレードできる「洗口液(せんこうえき)」について解説します。一般的に「マウスウォッシュ」として知られるこのアイテムですが、ドラッグストアにはたくさんの種類が並び、「どれを選べばいいの?」と迷ってしまいますよね。この記事で、ご自身の目的に合った最適な一本を見つけるヒントをお伝えします!
マウスウォッシュの役割と使う場面
マウスウォッシュは、液体でお口全体に行き渡らせることで、歯ブラシだけでは届きにくい場所の細菌を殺菌したり、口内環境を整えたりするオーラルケア製品です。
日常的な歯磨きの「仕上げ」として使うのが基本ですが、その他にも、人と会う前のエチケットや、食事後のリフレッシュ、就寝前に使って朝の口臭やネバつきを予防するなど、様々なシーンで活躍します。
「洗口液」と「液体歯磨き」は別物です
ここで、よく混同されがちな二つの違いをご説明します。購入の際はパッケージの表示を確認しましょう。
- 洗口液(マウスウォッシュ)
歯磨きの後に使い、口をすすぐことで効果を発揮します。あくまでブラッシングの補助的な役割です。 - 液体歯磨き(デンタルリンス)
歯磨き粉の代わりになるものです。口に含んで全体に行き渡らせた後、そのままブラッシングします。
お悩みに合わせたマウスウォッシュの選び方
マウスウォッシュの効果を最大限に引き出すには、ご自身の目的に合った成分配合の製品を選ぶことが不可欠です。お悩み別にチェックしたいポイントをご紹介します。
- 虫歯をしっかり予防したい
虫歯予防を一番に考えるなら、歯質を強化して酸に溶けにくい歯を作る「フッ素(フッ化ナトリウムなど)」が配合された製品を選びましょう。 - 歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)を予防したい
歯茎の腫れや出血といった歯周病のサインが気になる方は、原因菌へのアプローチが重要です。以下の成分に注目してみてください。
- 殺菌成分: CPC(塩化セチルピリジニウム)やIPMP(イソプロピルメチルフェノール)などが歯周病菌を殺菌します。
- 抗炎症成分: GK2(グリチルリチン酸ジカリウム)やトラネキサム酸が歯茎の腫れや炎症を抑えます。
- 口臭やお口のネバつきが気になる
口臭の主な原因は、細菌が作り出すガスです。原因菌そのものを減らすことが効果的なので、CPCなどの殺菌成分が高い製品がおすすめです。特に就寝前に使うと、翌朝のお口の不快感が大きく軽減されます。 - 刺激が苦手・お子様が使う
マウスウォッシュ特有のピリピリした刺激が苦手な方は、清涼剤として含まれるアルコール(エタノール)が原因かもしれません。刺激に弱い方やお子様は、「ノンアルコールタイプ」や「低刺激タイプ」と記載された製品を選びましょう。
必ず守ってほしい!マウスウォッシュの注意点
便利なマウスウォッシュですが、使い方を間違えると効果が半減してしまいます。大切な注意点を2つ覚えておいてください。
注意点①:歯磨きの「代わり」にはなりません
最も重要なポイントです。マウスウォッシュでは、歯の表面にこびりついたネバネバの汚れである「プラーク(歯垢)」を洗い流すことはできません。プラークは、歯ブラシやフロスで物理的にこすり落とす必要があります。
必ず毎日の丁寧なブラッシングを基本**とし、マウスウォッシュはあくまで補助的に使いましょう。
注意点②:使用だけで虫歯や歯周病は「治らない」
マウスウォッシュは、あくまで「予防」を目的とした製品です。すでに進行してしまった虫歯や歯周病を、これだけで治療することはできません。歯に痛みを感じたり、歯茎からの出血が続いたりする場合は、自己判断せず、必ず歯科医院を受診してください。
マウスウォッシュは、ご自身のお口の悩みに合った成分で選び、正しく使うことが大切です。毎日の歯磨きを基本とした上で効果的に活用し、お口の健康を守っていきましょう。
当院でも症状に合わせた製品を取り扱っております。「自分にはどれが合うの?」と迷われた際は、どうぞお気軽にスタッフまでお声がけください。
明石市、西明石駅徒歩1分の歯医者
にしあかし歯科 Tel:078-925-3333